
文房具の魅力

2020年から小学校の授業でプログラミング教育が必修化されます。…と言っても「そもそもプログラミングって何?」という人も多いかもしれませんね。子どもにも理解しやすく作られた教材やおもちゃを通して、“プログラミングの世界”をのぞいてみましょう!
プログラミングというと、パソコンのキーボードをたたきながら、暗号のような命令を画面に打ち込んでいく―。そんな難しげな印象はありませんか?
「それは昔のイメージ(笑)。プログラミング教育で子どもたちがすることとはまったく別物です」と滋賀リビングカルチャー倶楽部講師の東沢貴光さんは言います。
「プログラミング教育の雰囲気を体感できる」と東沢さんが薦めてくれたのが、文部科学省が開発した「プログラミン」。ITに苦手意識のある記者も挑戦しましたが、時間を忘れ、つい没頭。難しい理屈抜きで実際に動かしながらやり方を覚えられるので、誰でも楽しめそうです。
ところで、こうしたプログラミングを学校教育に導入する利点とは何でしょう? 「一つは問題解決能力が培われること」と東沢さん。
「例えば『画面上のキャラクターを動かしたい』と思った場合、それをプログラミングで実行するには『どの方向に』『どれくらいの距離を』『どれくらいの速度で』と具体的に考え、筋道を立てて命令する必要が出てきます。パソコンは人間と違ってあいまいな指示を理解できませんからね」
このように、答えにたどり着くまでの手順を自分で組み立てねばならないため、考える力が鍛えられ、ITを使う場面以外でも役に立つというわけです。
話を聞いたのは


サイトにアクセスすれば、誰でも無料で遊べる「プログラミン」。好きな動物などのイラストを選んで命令のアイコンを足していき、再生ボタンを押すと動物が動き出します。命令を出し間違えて動物が突如巨大化したり…といったハプニングもまた楽し、です

プログラミンでは「絵をうごかす」「絵の色をかえる」「音をならす」といったさまざまな命令がキャラクター化されています。これらを画面上で組み合わせながら作品づくりを行います
出典:プログラミン公式サイト=
http://www.mext.go.jp/programin/app/
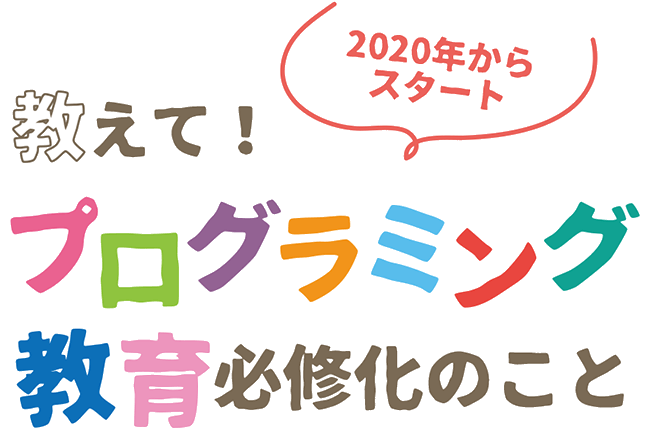
子どもたちがプログラミングを学ぶことにはどんな意義が? 東沢さんに聞きました。
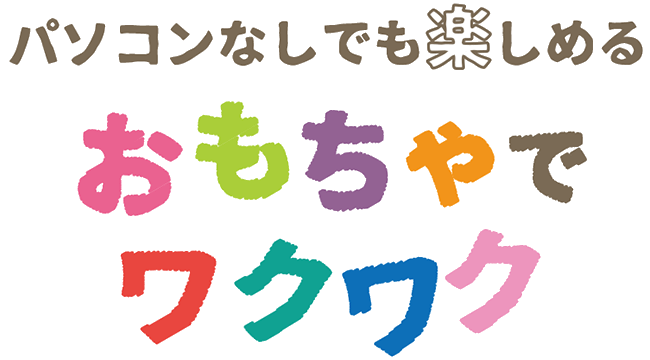
パソコンを起動させなくても、プログラミングの面白さが簡単に体感できるおもちゃを紹介します。

「前進」「右折」「左折」「サウンド」といった動きを命令するパーツを組み合わせ、イモムシを動かします。パーツの並べ順や個数を変えて、いろんな動きを試してみましょう。ピカピカ光りながらゆっくり進む様子がかわいい!

進む方向などを指示する「めいれいタグ」をくるまにかざし、「ぼうけんマップ」と呼ばれるコース上を走らせます。どのタグをどの順にかざせば思った通りに動くのかが考えどころ。同じ命令を繰り返す「ループ」と呼ばれるタグなども使えば、複雑な指示も簡単に出せますよ。