
「こそだて1コマ劇場」【こそだてDAYS】
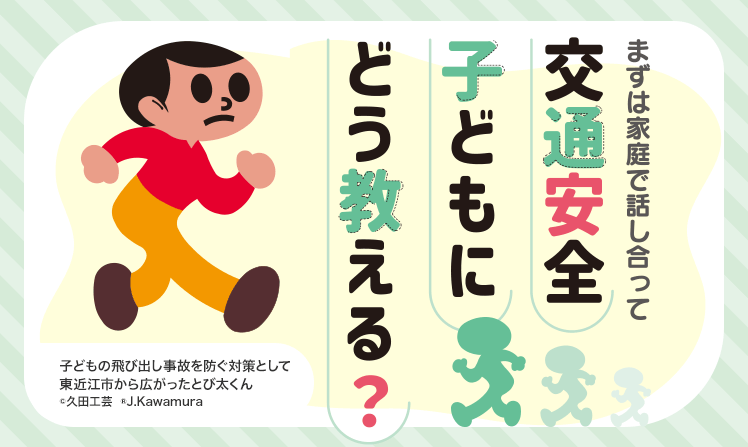
入学式や新学期を迎える春。春休みなど外出の機会が増えるこの時期は、子どもの交通事故が心配という人も。そこで、子どもの人身事故の状況や、事故防止のために周りの大人ができることについて取り上げます。
滋賀県警察本部によると、令和6年に滋賀県で起こった未就学児・小学生の人身事故件数は66件。負傷者139人のうち、歩行中のケガが36人で、自転車走行中のケガが37人。歩行中は走行車両の直前横断や飛び出し、自転車では交差点での出会い頭の事故が多いようです。
「大人抜きで出かける〝一人デビュー〟や〝自転車デビュー〟、また新年度を迎えるこの時期は、新小学1年生の登下校の事故などが特に心配されます。家庭、地域で子どもを事故から守るという意識が必要です」と、滋賀県警察本部交通部交通企画課の木枝和行さん。
「子どもに見られがちな行動特性(下記)を周りの大人が把握し、事故につながる行為や交通ルールを家庭内で教えてあげて」と呼びかけます。
一方、子どもの交通事故で最も多いケースは、実は車の同乗中の事故。負傷者139人のうち63人の半数近くが同乗中にケガをしています。「惨事を防ぐために、子どもが小さいうちからシートベルトやチャイルドシートの着用を癖づけるなど、当たり前のことにするのが大切です」
4月6日(日)~15日(火)は、「春の全国交通安全運動」が行われます。また滋賀県では、4月15日まで「新入学(園)児と高齢者の交通事故防止運動」を独自に実施中。
この機会に、家庭内で交通安全について話し合いませんか。親が子どもにどうやって交通安全について伝えたらよいか、ポイントを聞きました。
通園・通学路で多い交通事故を防ぐためには?
「保護者とお子さんがルートを一緒に歩き、危険な箇所や道路標識の見方などをチェックしておきましょう。その際、例えばカーブミラーを見つけたら『相手から見えにくいところにミラーがあるんだよ。〇〇ちゃんもミラーを見て車や自転車が来ていないか確認しようね』など、何に注意するのかを具体的に伝えて。子どもは大人よりも視野が狭く、大人に見えているものが見えていない場合があります。子どもの目線に合わせることを忘れないで。
周りの音を意識すること、横断歩道を渡るときはドライバーが気づきやすいように手をあげることなど、耳や手を使うことも教えてあげましょう」
通学路以外にも、よく行く公園などもチェックしておきたいですね。

出合い頭の衝突が多い自転車走行中の事故を防ぐには?
「車の往来が多い道や慣れない道はなるべく避けること。そして『自転車安全利用五則』(※1)の交通ルールはきっちり教えましょう。特にヘルメットの着用は徹底してほしいですね。ヘルメットがある・なしで致命傷のリスクが大きく変わるにも関わらず、滋賀県民のヘルメット着用率は全国平均を下回っています。親がかぶらないと、子どももかぶりたがりません。まずは親がお手本になって、子どもに習慣づけを。
標識に注意することも必要です。自転車は車の仲間ですので、『止まれ』の標識があれば一時停止をしなければなりません。標識のない交差点でも、徐行や安全確認を徹底することで事故を避けられることを伝えましょう」

車の動きが不規則な駐車場でのアクシデントも珍しくありません。
「駐車場は停車している車や柱など死角が多く、ドライバーにとって小さな子どもは見えにくいので注意が必要です。
駐車スペースに車を止めた場合、子どもに『勝手に車から降りて飛び出さないように』と言い聞かせ、大人が先に降りて安全を確保してから降ろすようにしましょう。また、子どもは止まっている車を危険視しない傾向がある点にも注意を。停車している車が駐車スペースからいきなり出てきたり、前進していた車がバックで駐車を始めたりなど、どこから車が来るのか子どもには予測できていないことも多いようです。
駐車場内では子どもが一人で動き回ることがないように、必ず大人と手をつないで歩くように教えてください」

ドライバー側も注意!
車を運転する大人側も、最善の注意を払うことが大切です。
「ふいに道路側にはみ出すなど思わぬ行動に備えて、子どもを見かけたら速度を落とし、間隔を空けて走行を。横断歩道を渡ろうとしていたら必ず一時停止をし、横断者が渡り切るのを見届けてから発進しましょう」(木枝さん)。
滋賀県警察本部では、関係機関と連携して「横断歩道利用者ファースト運動」(※2)を推進。これが功を奏しているのか、JAF(日本自動車連盟)の調べによると、滋賀では信号機のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているときの車の一時停車率が、令和3年は20.7%と全国平均を下回っていたものの、令和6年には68.6%まで上昇。全国平均の53%を上回っているとか。
「令和6年の事故による県内全体の死者数は28人で、前年より15人減と大幅に減ったのは、こうした交通安全に対する意識の向上が影響しているのかもしれません」
今後も思いやりのある運転を心がけ、命を守っていきたいですね。
イラスト/フジー