
私たちのまわりの空き家事情

9月末から始まるNHK朝の連続テレビ小説「スカーレット」の舞台は信楽! ということで、その信楽で、夏の暮らしがちょっとすてきになる陶器を探してきましたよ。
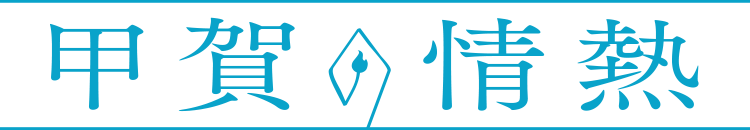

独創的なフォルムと神秘的なブルーが、夏の食卓に映えそうな藤原純さんの器。じっと見ていると宇宙に吸い込まれていくような不思議な雰囲気をたたえています。
「形は使いやすくシンプルに、縁のラインで動きを出す」のが藤原さん流。砂の入った粗い陶土を使い、頭にあるイメージを自由に形にしていきます。釉薬は厚めにかけ、約1300℃の高温で焼成。灯油窯で焼くことで煙などの不純物が生地に入り込み、独特の風合いが生まれます。発色や釉薬の動きなど焼き上がってみないとわからない部分も多いそう。
「自由にオブジェをつくるように、器でも自分の世界観を出したい。その中でぼくの内にある「信楽」が自然ににじみ出たらいいですね」。使っている間に色や手触りも変化していくとのこと。普段使いしていろんな料理との相性を楽しんでみては。

古仙堂藤原純さん

赤土の素地に白い化粧泥を施す〝粉引き〟と呼ばれる伝統技法で作られたカップアンドソーサー。あたたかみのある白色に、〝呉須(ごす)〟という染料で描かれた青い線があしらわれています。涼しげな風合いと丸みのある素朴なフォルムは、冷製スープやデザートを入れる器として夏にも活躍しそう。低めの温度で2度本焼きを行うため、水分がしみにくく丈夫。気軽に毎日使いやすいのも魅力です。
「粉引きの白は料理を優しい表情に見せてくれる色。この素材感が好きなんです」と語る作者の古谷浩一さんは、韓国発祥の粉引きの技法を信楽焼きに取り入れ普及させた陶芸家・古谷信男さんの長男。21歳から父のもとで作陶を始め、器作りの技と心を学びました。「父から受け継いだものを大切にしつつ、今のライフスタイルに合ったデザインや表現に挑戦していきたいですね」

古谷製陶所古谷浩一さん

白泥の白と土肌の黒。「文五郎窯」の奥田章さんがつくるモノトーンの器は、いわゆる〝信楽焼らしい〟陶器とは一線を画すスタイリッシュさ。ツヤ感を抑えたシックな風合いは、和洋どちらの料理でもオシャレに使えます。
「本当に自分らしいものを作りたい」と語る奥田さんの作品のアイデアは、日常生活の中に見つけることが多いのだとか。例えばオリジナルの「十草(トクサ)」の文様は、ギャラリーの借景の竹林からインスピレーションを得たもの。またリバーシブル皿を思いついたのは、なんと「愛用しているフリース素材の上着がリバーシブルデザインになっているのを見て(笑)」。ただ表裏が使えるだけでなく、持ったり重ねたりした時にも使いやすいように改良を重ねている点も見逃せません。細部にまで研ぎ澄まされたデザインに「器は日常で使ってこそ」という奥田さんの思いがあふれています。

文五郎窯奥田章さん

土の風合いを残す陶器の水槽で泳ぐ金魚たちはどこか心地よさげ。明山窯の陶水槽は、2009年に登場した夏の人気製品です。
「代表的な信楽焼の一つにメダカ鉢がありますが、魚の様子を横から見られたら…という思いが開発のきっかけでした」と石野昇さんは話します。ガラスとのコラボは同窯にとっても初めての試み。陶器は焼くとひずみが生じるため、ガラスと組み合わせると隙間ができてしまいます。丈夫で見やすくかつ水漏れがしない形状や、ガラスを接着するシリコンボンドの工夫など試行錯誤を重ねて完成。「メダカの孵化を間近で見られたときは感動しました」と頰を緩める石野さん。陶器の持つ特性により外気温に左右されにくく、水換えや掃除も少なくて済むなどのメリットも。また使い道は自由自在。水草のアクアリウムとして、多肉植物の鉢として自由な発想で生活を彩れそうです。

明山窯石野昇さん

日本六古窯(にほんろっこよう)のひとつ、信楽焼。あなたは何を思い浮かべますか? 今回取材した人たちに改めて「信楽焼とは?」 と尋ねてみたら、 こんな回答が返ってきました。
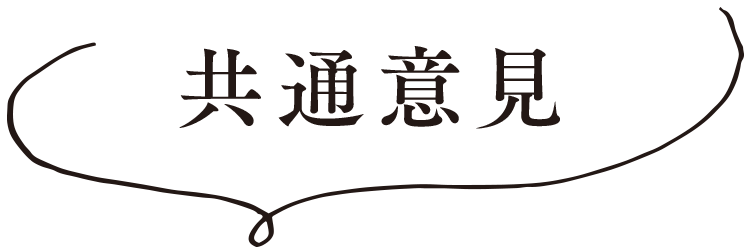
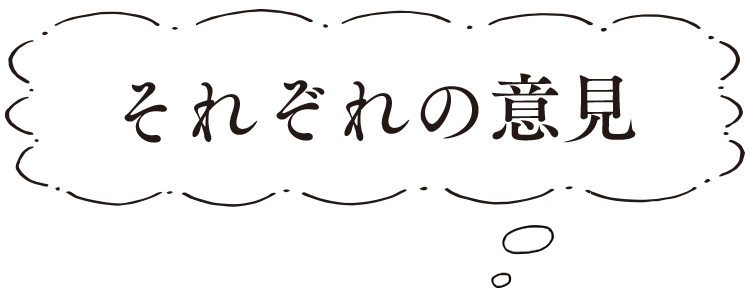
〝土の味〟を楽しむもの。独特の柔らかさ、ユルさがあると思います
藤原純さん
信楽の風土が醸し出すおおらかでカチッとし過ぎていない雰囲気
古谷浩一さん
他と比べて縛りが少ない。日常に使うあらゆる陶器をつくる産地
奥田章さん
伝統的な技術を大切にする心と、新しいものを取り入れる心が息づいている陶器です
石野昇さん
種類の豊富さ、柔軟で自由な作風は、信楽焼の特徴の一つのようです。産地に出かけて、今まで知らなかった〝MY信楽焼〟を見つけてみては?